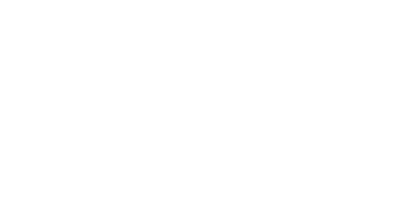Works事例・実績
東証プライム上場 BPOコンサルティング企業
業績は好調なのに、認知度や事業内容に対する社会の理解不足が悩み。PRによるリブランディングで、企業イメージを刷新&業績もさらに上昇
創業当初からの事業で先駆けとして知られるA社は、広範な業種を対象とした各種BPO(業務支援)やコンサルティング、コンテンツの企画・制作まで手がけるまでに成長を遂げています。
株式上場も果たし、常に業績は好調。
しかし、取引先以外の間では認知が高まらず、事業内容への理解ももの足りない状態が続いていました。
この状況を打破したのは、広報戦略でした。

目次 ・・・
課題
・創業以来市場の先駆けとして推進する基幹事業のイメージが強すぎて、AIサービスをはじめとした幅広い分野への参入や新規事業に対して、社会の理解が深まらない。
・企業規模の大きさや業績の良さに対して、取引先以外には認知が低い。
・企業規模の大きさや業績の良さに対して、取引先以外には認知が低い。
目的
・基幹事業以外の市場における優位性を、幅広くメディアにアピール。
・BPOやコンサルティング等も含め、広範囲にわたる事業内容について、社会に理解を深めてもらう。
・ステークホルダーがA社を選ぶ必然性を伝え、業績に反映させる。
・BPOやコンサルティング等も含め、広範囲にわたる事業内容について、社会に理解を深めてもらう。
・ステークホルダーがA社を選ぶ必然性を伝え、業績に反映させる。
手法
・広報戦略の策定により、リブランディング(ブランドイメージの変革)を提案。
・3C分析+メディア分析でA社の現状把握を行い、それを参考に企業の紹介方法やプレスリリースの書き方の変更を提示した。さらにアプローチメディアの見直しを行ったうえで、広報活動を進めるようにした。
・企画や記者別に、個別のアプローチを仕掛け、希望通りのテーマによる取材を増やした。
・3C分析+メディア分析でA社の現状把握を行い、それを参考に企業の紹介方法やプレスリリースの書き方の変更を提示した。さらにアプローチメディアの見直しを行ったうえで、広報活動を進めるようにした。
・企画や記者別に、個別のアプローチを仕掛け、希望通りのテーマによる取材を増やした。
成果
・これまで露出が少なく、BPOやDX、AI等の取材が欲しかったことで重点メディアに設定したIT系媒体を含め、前年比の約2倍の露出を獲得。
・寄稿記事に、大学教授や大手企業の役員等、影響力のある人々から好意的リポストがあり、リブランディングに寄与。
リブランディングとは、商品・サービス、企業そのものがこれまで培ってきたブランドイメージを再構築する戦略です。
A社の場合、創業時からの看板である基幹事業のパイオニアとしてのイメージが強すぎて、企業の本来のポテンシャルをアピールしきれていないもどかしさが課題でした。
これを払拭するための広報戦略を策定し、リブランディングを試みたのです。
広報戦略とは、ステークホルダーと企業がコミュニケーションを図る際に、一貫して遵守すべき指針です。広報戦略の策定により、一貫して正確に企業のメッセージを送り続けることができるようになります。時流や社会情勢が変化しても、統一したブランドを保ち続けられるようになるのです。
広報戦略に関しては、別の解説を参照していただきたいのですが、自社の課題を洗い出し、現状を分析し、広報活動によって解決できる項目を整理します。そして具体的な手法を検討するというのが、大まかな流れです。
広報戦略とは: https://mops-pr.net/prkyoukasyo/howto_kouhousenryaku/
A社の場合は「課題」はすでにわかっていますので現状を分析するところから始めます。
これには、3C+メディア分析を利用しました。
3Cとは、Customer(顧客、市場)/Competitor(競合)/Company(自社)を指し、この3つの観点から自社の現状を分析するフレームワークです。
自社の強みや弱みを分析し、さらに競合の動向・現状も見ていきます。そこから成功要因の発掘方法を探り出していくのです。
これに自社や競合がどのように報道されているのかを把握するためのメディア分析を組み合わせ、具体的な広報計画を作成します。
A社の場合は、同業他社に比べて基幹事業の実績が多いところから、顧客接点のノウハウや人材が蓄積されている点に優位性があるとわかりました。
また、顧客からの膨大な量の問い合わせ内容がデータとして収集できていて、これも大きな武器になりそうです。
さらに、筆頭株主となる大手企業との協業が今後活性化し、成長が見込まれることも強みでしょう。
このようなA社の同業他社にはない特徴が際立つように、事業モデルやユニーク性にフォーカスを当てて報道用のファクトシートを制作しました。そして、あらゆるテーマの取材であっても、このファクトシートを配布し、A社の「あまり知られていない魅力」について訴求し続けたのです。
さらにこれまで露出がいまひとつだったBPOやコンサル等の事業に取材が来るように、集中的にアプローチをかけたほか、寄稿連載も取り付けました。
その結果、露出するメディアの傾向に変化が出て、媒体の種類も数も前年比2倍という結果となったのです。露出結果を資料として営業にも活用することで、成約率が向上したことはもちろん、企業イメージそのものが高まり出し、リブランディングの第一歩を踏み出すことができました。
広報戦略に関するお問い合わせはこちらから。
・寄稿記事に、大学教授や大手企業の役員等、影響力のある人々から好意的リポストがあり、リブランディングに寄与。
リブランディングとは、商品・サービス、企業そのものがこれまで培ってきたブランドイメージを再構築する戦略です。
A社の場合、創業時からの看板である基幹事業のパイオニアとしてのイメージが強すぎて、企業の本来のポテンシャルをアピールしきれていないもどかしさが課題でした。
これを払拭するための広報戦略を策定し、リブランディングを試みたのです。
広報戦略とは、ステークホルダーと企業がコミュニケーションを図る際に、一貫して遵守すべき指針です。広報戦略の策定により、一貫して正確に企業のメッセージを送り続けることができるようになります。時流や社会情勢が変化しても、統一したブランドを保ち続けられるようになるのです。
広報戦略に関しては、別の解説を参照していただきたいのですが、自社の課題を洗い出し、現状を分析し、広報活動によって解決できる項目を整理します。そして具体的な手法を検討するというのが、大まかな流れです。
広報戦略とは: https://mops-pr.net/prkyoukasyo/howto_kouhousenryaku/
A社の場合は「課題」はすでにわかっていますので現状を分析するところから始めます。
これには、3C+メディア分析を利用しました。
3Cとは、Customer(顧客、市場)/Competitor(競合)/Company(自社)を指し、この3つの観点から自社の現状を分析するフレームワークです。
自社の強みや弱みを分析し、さらに競合の動向・現状も見ていきます。そこから成功要因の発掘方法を探り出していくのです。
これに自社や競合がどのように報道されているのかを把握するためのメディア分析を組み合わせ、具体的な広報計画を作成します。
A社の場合は、同業他社に比べて基幹事業の実績が多いところから、顧客接点のノウハウや人材が蓄積されている点に優位性があるとわかりました。
また、顧客からの膨大な量の問い合わせ内容がデータとして収集できていて、これも大きな武器になりそうです。
さらに、筆頭株主となる大手企業との協業が今後活性化し、成長が見込まれることも強みでしょう。
このようなA社の同業他社にはない特徴が際立つように、事業モデルやユニーク性にフォーカスを当てて報道用のファクトシートを制作しました。そして、あらゆるテーマの取材であっても、このファクトシートを配布し、A社の「あまり知られていない魅力」について訴求し続けたのです。
さらにこれまで露出がいまひとつだったBPOやコンサル等の事業に取材が来るように、集中的にアプローチをかけたほか、寄稿連載も取り付けました。
その結果、露出するメディアの傾向に変化が出て、媒体の種類も数も前年比2倍という結果となったのです。露出結果を資料として営業にも活用することで、成約率が向上したことはもちろん、企業イメージそのものが高まり出し、リブランディングの第一歩を踏み出すことができました。
広報戦略に関するお問い合わせはこちらから。